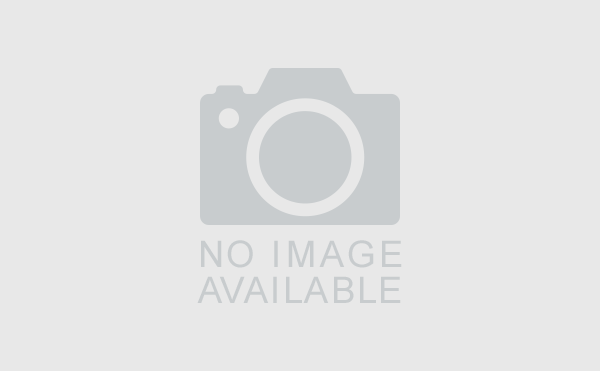尿路結石(シュウ酸カルシウム結石)の予防

犬と猫の尿路結石で近年増えているのがシュウ酸カルシウム結石です。
昔はストラバイト結石が圧倒的に多かったのですよね。しかし、市販のものを含め猫ちゃんのフードの大半がストラバイト対策(尿の酸性化)されるようになり、犬のストラバイト結石はほとんどの場合が尿路感染が原因であることの周知が広がり、ストラバイト結石が問題になることは少なくなりました。
それに代わって増えてきたのがシュウ酸カルシウム結石です。
ストラバイト対策フードのほとんどのものには、シュウ酸カルシウム結石の予防にもなると書いてあります。書いてありますが、ストラバイトは酸性で溶解するのに対し、シュウ酸カルシウムは酸性で析出しやすくなるとされています。同じフードで両方を上手くコントロールするのは無理があります。
シュウ酸カルシウム結石は、その形成機序が完全に解明されておらず内科的な管理が難しいです。なかなかフードだけでの管理は難しいですが、比較的上手くいくフードもあります。ヒルズのu/dです。
u/dはその他の内服薬を併用することなしに比較的再発を予防できますが、このフードは低蛋白食です。老齢期の犬には使用を検討しますが、若齢から長期に与え続けるのはタンパク質欠乏のリスクがあり推奨できません。
じゃあ、どうするのか。
当院では、まずはヒルズのc/dやロイヤルカナンのユリナリーs/oなどのストラバイト/シュウ酸カルシウム予防のフードと、クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム内服薬の処方を行います。
それでも上手く行かない場合は、尿中へのカルシウムの排泄を抑制する利尿剤の一種であるヒドロクロロチアジドを併用します。
それでも再発が問題になる場合はu/dを与えることを検討します。
「当院では」と書きましたが、これはガイドライン(正しくはコンセンサスステートメント)に書いてあることなのです。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/javnu/11/1/11_41/_pdf/-char/ja
上記のACVIMコンセンサスステートメントに以下の記載があります。
・推奨3.3b
酸性尿が持続している犬ならびに猫には、クエン酸カリウムその他のアルカリ化クエン酸塩の投与を検討する。
・推奨3.3c
シュウ酸カルシウム尿路結石が頻繁に再発する場合は、チアジド(サイアザイド)系利尿薬の投与を検討する。
これは2016年のガイドラインですからもう10年近く経つわけで、何で今更こんな古い話題を上げているのかというとですね、このガイドラインがあまり浸透していないからです。
同じガイドライン(ACVIMコンセンサスステートメント)でも、犬の僧帽弁閉鎖不全症のガイドラインの浸透度は凄いと思います。日本のほとんどの小動物臨床獣医師が概要を知っていると思いますし、大抵の動物病院で正しく活用されています。
それに比べると、この尿石症管理は同じ米国獣医内科学会が発表しているのですが今一つ浸透度が低いみたいです。
シュウ酸カルシウム結石だと言われた/言われて手術もしたし、それでフードを代えるように言われてその後何もしていない。という飼い主さまがもしいらっしゃいましたら要注意です。再発している可能性が高いです。
シュウ酸カルシウムは形成機序が解明されておりませんので、現在の獣医学で正しいとされている対応をしても再発することがあります。しかし、せめてガイドラインに沿った対応をした方が良いのは間違いありません。
シュウ酸カルシウムは内科的に溶解はできません。せっかく手術したのにまた再発して膀胱炎で愛犬愛猫が苦しむのはかわいそうですよね。
愛犬/愛猫の尿路結石でお悩みの飼い主様は、標準治療を理解し実践している、はら動物病院を是非ご利用ください。