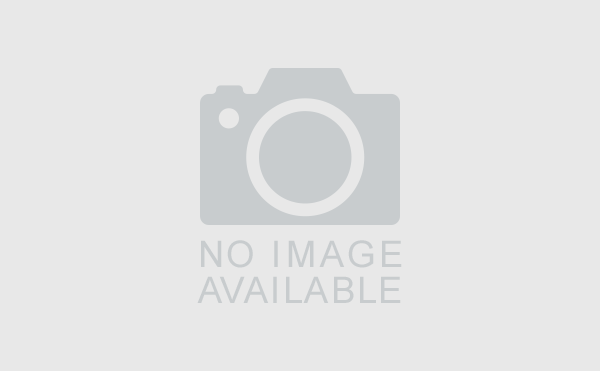不明熱として抗生剤試験投与されていたFIP症例


トップ画像は猫ちゃんの胸水とリバルタテストの写真です。
獣医療関係者や猫に詳しい人ならもうおわかりですね。FIP症例です。
本例は、発熱があって元気・食欲がなく、血液検査では原因が不明で抗生剤の試験投与を受けたが良くならない、ということでご来院されました。
特定の症状に関する診断手順というのはある程度の型があります。発熱に対するアプローチもある程度決まっております。発熱があって状態が悪い動物に対しては、血液検査・尿検査・胸/腹部レントゲン検査・腹部/心エコー検査・感染症の検査を行います。症状があいまいで発熱が続く場合は関節穿刺も推奨されます。
感染症の検査とは、犬ならバベシア、エールリヒア、アナプラズマ、SFTSなどで、猫ならFIP、FeLV/FIV、トキソプラズマ、バルトネラ、アナプラズマ、SFTSなどです。
感染症の発生には地域性がありますので、その地域では稀な感染症で旅行歴もなければ検査の必要性が下がるものもありますが、犬猫にはこのような感染症が知られています。
元の動物病院さんに再診に行かれていれば同様の検査を行ったのではないかと思いますが、人と人とのコミュニケーションは齟齬が生まれることがあります。当院では必要な検査をしっかりおすすめしているつもりですが、飼い主様がどうとらえていらっしゃるのかは最終的にはその人にしかわかりません。
「何か合わないな」と思われたら別の動物病院にかかってみると解決するかもしれません。
当院の場合には、必要があれば幅広い検査をすすめたり、様々な可能性の話をして断言はあまりしないので、そういうのが嫌な飼い主様には合わないかもしれません。しかし、逆に、「あんまり検査してくれなくて愛犬/愛猫の診断治療がなかなか進まない」とお悩みの飼い主様には当院が合うかもしれません。
本症例はレントゲン・エコー検査で胸水を認め、胸水の性状は滲出液でFIPが疑われました。
高齢で2頭飼育ということでFIPの可能性は低そうな飼育環境・年齢でしたが、胸水の一般的な性状検査や、リバルタテストからFIPが疑われる状況で、飼い主様が早期治療をご希望されたため、PCR検査の結果が出る前にモルヌピラビルの投与を開始しました。
リバルタテストとは、酢酸水溶液に胸腹水を垂らして、クラゲ状に下まで沈んだり線上に残ったりして消えない場合はFIPの疑いが高くなるという検査です。FIPではない場合はけむり状に消えて見えなくなるとされています。学術的に確立された方法とは言えませんが、補助的に行ったリバルタテストでも明らかな陽性ということもあってPCR検査結果が出る前にモルヌピラビル投与に踏み切りました。
リバルタテストに関しては以下をご参照ください。
https://yukonishiyama.com/fip-risk-factor/
その後胸水のPCR検査結果が出てFIPであることが(臨床的には)確定しました。
基本的には抗微生物薬の試験投与というのは極力控えるべきです。抗生剤も高ウィルス薬も抗真菌剤も乱用によって耐性菌・ウィルスが生まれます。
実際に、当院ブログをご覧になってモルヌピラビルの処方をご希望でいらした症例で、処方をお断りしたこともあります。当院で検査をしていないので詳細は不明ですが、その症例のその後の経過はFIPである可能性が低いようでした。
乱用はしてはいけませんが、症例の状態や飼い主様のご希望を踏まえて診断確定前に治療を開始することはあります。
当院では、飼い主さまの同意がいただけるのであれば、積極的に速やかに必要な検査を進めるように善処しております。
愛犬/愛猫の病気の状況がなかなか改善されずにお困りの飼い主様は、はら動物病院への受診をご検討ください。