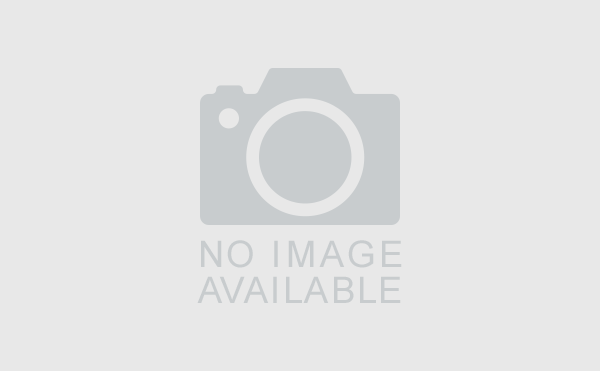肝臓値を正常化する
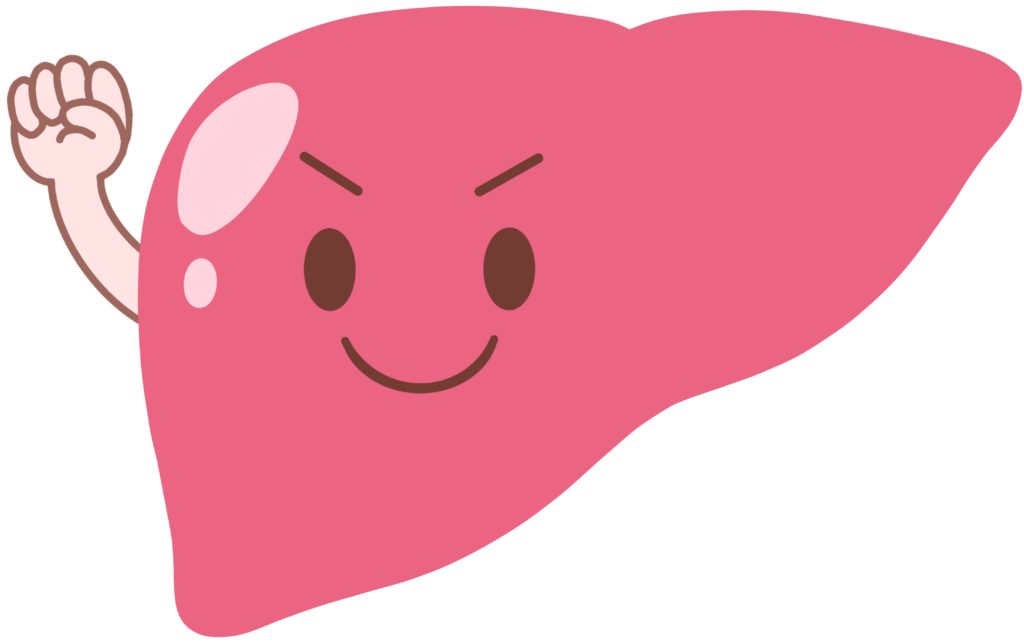
健康診断でひっかかりがちですよね。肝臓値。ALT(GPT)とかALPとか。
正常値にこだわる必要がどこまであるかは不明です。おそらく軽度な高値は生命予後(寿命)には影響しない可能性の方が高いです。
じゃあ問題ないのかと言われると、そこはわからないわけです。若いころは正常だったのに中高齢になってから軽度高値が続いていると気になりますよね。
本稿は、他に異常が見つからず、ウルソデオキシコール酸やSAMeサプリメントなどの一般的な治療はしてみたけれども、正常値にならない、かといってそんなに高値でもない。問題ないのかもしれないけれども、下がるものなら正常化したい、そんな飼い主様向けに、当院だったらどんなことができるかな、という記事です。
他に異常がない前提です
肥満や高脂血症、クッシング症候群や甲状腺機能低下症、肝臓の腫瘍や胆道結石など、原因となるような異常がないかどうかはしっかり検査をしましょう。食前食後の総胆汁酸(±アンモニア)濃度も測定しておきましょう。
もし原因が見つかれば原因に対する治療を行いましょう。
健康診断の一般的な項目の血液検査や、必要があればホルモン検査、レントゲン・エコー検査を行って、体型も肥満ではない。でも肝酵素が高い。そして広く使われるウルソデオキシコール酸やサプリメントも併用もしたけれども、それでも正常化しない。そんな場合が前提です。
まずはしっかり検査しましょう。それで何も問題なければ一般的な薬を使ってみましょう。
本稿はその先の話です。
治療の必要があるのか?
たぶんないんですよ。「たぶん」」ね。
でも気になるし、「たぶん」は誰にも外せないんですよ。だから気になるんですよね。
標準治療+α
ウルソやSAMeや、場合によってはビタミンEくらいまでは標準治療かもしれないですね。
それでも正常値にはならない。かといってALT(GPT)値として200 U/l未満程度で、肝生検までした方が良いほど重症とも言えない。このままでも問題ないような、でも後々もっと悪化したらかわいそうだし、できることがあるならやってあげたい。
そんな場合の+αの選択肢を考えます。
①整腸剤
腸内細菌叢のバランスの悪化や、腸管のバリア機能の悪化が肝酵素上昇を招いている可能性があります。
整腸剤は、毒素を産生する悪玉菌を減らしたり、毒素が腸管バリアを突破して門脈に流入するのを防ぐ作用が期待できます。
また、親水性胆汁酸を増やすことで胆汁による肝細胞障害を減らしたり、抗酸化作用によって肝細胞を保護する効果も期待できます。
ただ、整腸剤と言っても様々な種類があります。
犬に対して、整腸剤の投与で肝酵素の低下作用が確認されたという論文は、私の知る限りはイタリアのFlorentero ® Candioliだけですが、残念ながら国内では販売されておりません。
https://www.mdpi.com/2306-7381/11/8/364?utm_
国内で手に入る製剤で、かつ前臨床データやその他の知見から、どの製剤を選ぶのかということは非常に大切です。整腸剤は動物用医薬品ではないサプリメントがほとんどで、玉石混合です。
②スピロノラクトン
整腸剤ほど気軽に使えませんが、ミネラルコルチコイド受容体(MR)拮抗薬のスピロノラクトンも選択肢になるかもしれません。
肝疾患に対してこの薬を使うのは、一般的には肝硬変などでの門脈高血圧からの腹水に対する治療薬というイメージです。しかし、特定の状況下においては早期投与を検討しても良いかもしれません。
特定の状況とは、原発性門脈低形成や僧帽弁閉鎖不全症がある場合です。
肝硬変モデルラットを用いた研究では、肝臓の血管収縮と線維化の抑制が確認されています。
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0034230&utm_
②-1 原発性門脈低形成とスピロノラクトン
原発性門脈低形成は、先天的な肝臓内の門脈枝の低形成です。若齢時に(仮)診断がついている場合もありますが、無症状例がほとんどなので未診断のまま中高齢になることも多いです。
詳細は省略しますが、門脈低形成から門脈高血圧になっている場合には、高アルドステロン血症が肝内血管の収縮や組織線維化を助長している可能性があります。MR拮抗薬によりこれらの悪影響を緩和できる可能性があります。
とはいっても、確実に高アルドステロン血症が生じているだろうと言えるのは、それなりに進行した状態だと思われますので、今回のテーマである、軽度な症例に気軽に使う薬ではないと思います。
②-2 僧帽弁閉鎖不全症とスピロノラクトン
小型犬に非常に多い心臓病の僧帽弁閉鎖不全症では、循環不全に対する代償機構として高アルドステロン血症を生じている場合があります。
このことで②-1と同様の問題が生じているかもしれません。MR拮抗薬を試しても良いかもしれません。
ただ、僧帽弁閉鎖不全症で明らかな高アルドステロン血症が生じるのも、やはりそれなりに進行して循環不全傾向になってからだと思われます。(議論があるところかもしれません)
ACVIMのstageB2以上の僧帽弁閉鎖不全症があるのであれば、スピロノラクトンを試してもよいかもしれません。僧帽弁閉鎖不全症の予後改善効果もあるかもしれないですし。
もし投薬するなら腎臓値や電解質のモニタリングが必要でしょう。
③テルミサルタン
犬猫の臨床では、高血圧とタンパク尿に対する薬として使われます。
この薬はアルドステロンの生成刺激となるAT1受容体拮抗薬ですのでスピロノラクトンと同様にアルドステロンによる有害作用を低減します。
また、AT1受容体刺激による作用はアルドステロンの生成だけでなく、血管収縮や組織線維化の助長などの作用があるとされています。
テルミサルタンの作用で肝臓の血流改善や線維化進行抑制が期待できる可能性があります。
ロサルタンは人のC型肝炎慢性期の進行抑制が期待できるようです。
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4876242/#:~:text=Losartan%20may%20inhibit%20the%20progression,led%20to%20regression%20of
犬猫でロサルタンの使用データは少ないので、応用するなら一般によく使われるテルミサルタンの方が安心かなと思います。
しかし、低血圧や腎臓の糸球体濾過量の低下の副作用懸念があるので、腎臓値や電解質、血圧のモニタリングが必要です。
ACVIM stageB2以上の僧帽弁閉鎖不全症があって、かつ肝酵素上昇がある場合には試してみる価値があると思います。
似た薬のACE阻害剤であるベナゼプリルやアラセプリルでも良いかもしれませんが、ACE阻害薬は長期投与でアルドステロンブレイクスルーという作用の減弱が生じやすいと言われています。
このため、僧帽弁閉鎖不全症ではACE阻害剤とスピロノラクトンの併用が推奨されますが、僧帽弁閉鎖不全症がまだ軽度な状態で肝臓値上昇対策も兼ねて1剤だけ加えるならテルミサルタンが良さそうです。(個人的な意見です)
有力なのは整腸剤
スピロノラクトンは一応利尿剤カテゴリーですので、なんとなく腎臓への影響が気になりますし、私は利尿剤の腎毒性というものは直接的にはないと思っている派ですが、電解質への影響は出るわけですし、気軽に使える薬ではないです。
しかも臭いんですよね。小型犬用に人の製剤を分割するとさらに臭いが強くなってしまいます。硫黄の臭いがするので、「もしかしたら良いかも」くらいで長期投与するのはなかなか厳しい薬です。
テルミサルタンは、僧帽弁閉鎖不全症を持っている子に対しては有力な選択肢になると思います。
しかし、心腎疾患のない場合に肝酵素上昇のみに対して使うかといわれると躊躇われます。副作用も多少ありますし。
それに対して整腸剤は害がないわけでして、安心して使えるのがとても良いところです。
人の方でもヤクルト1000が人気みたいですよね。良い菌株であることに加えて、数が多いことが大切です。悪玉菌と戦うには善玉菌の大軍が必要です。少数では負けてしまいます。
当院では、日本国内で正規販売されている動物用整腸剤の中で、メーカー推奨投与量における菌数(CFU)が最も多い整腸剤を使用しています。善玉菌の大軍が悪玉菌を圧倒します!
当院では、こんな感じで生理学的な知見をあれこれ考えていろいろ調べた上で、標準的ではない処方も飼い主様のご希望と同意があれば実施しておりますので、愛犬愛猫の慢性疾患でお悩みを抱えている飼い主様は、はら動物病院にご来院ください。