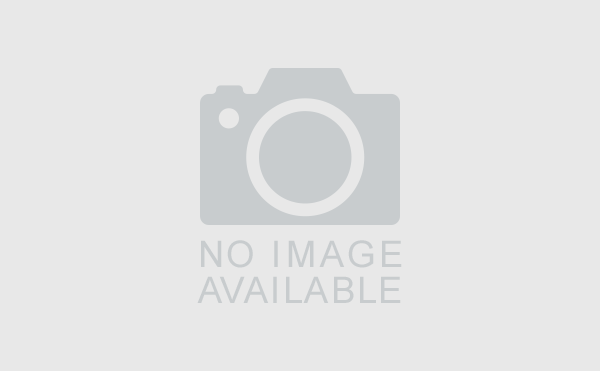犬の甲状腺機能低下症は誤診率50%以上?

犬の甲状腺機能低下症とは
犬の甲状腺機能低下症は、最も一般的には慢性甲状腺炎に伴う甲状腺萎縮により、甲状腺ホルモンの分泌が減る病気です。
甲状腺ホルモンには様々な作用がありますが、代謝を活発に元気にする作用があるホルモンです。
このため、肥満、被毛菲薄化、貧血、高脂血症があらわれるのが典型的です。
典型的ではない症例の場合、症状として昏睡や末梢神経障害、不整脈などが出ることもあります。
また、慢性甲状腺炎以外の原因として、ごくまれに脳下垂体腫瘍が原因の中枢性甲状腺機能低下症があると言われています。
甲状腺機能低下症は誤診が多い病気として有名
イギリスの論文ですが、一次診療で甲状腺機能低下症と診断され、甲状腺ホルモン剤の投与を受けた症例に関して、3名の獣医内科認定医がその妥当性を評価したところ、それぞれ58.8%、52.9%、45.1%の症例でホルモン剤の投与の妥当性がないと判断した、という論文があります。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.16993
日本は一次診療動物病院の診療レベルが高い国だと思っています。最先端の研究はアメリカなど諸外国にかなわない面が多いと思いますが、一次診療の平均レベルは高いと言われており、誤診率もここまで酷くはないのではないかと思います(思いたい!)。
しかし、お引越しやその他の理由で既に甲状腺ホルモン剤を飲んでいる症例を診ることになった場合には、そもそもの診断の妥当性には気をつけるようにしています。
急性期に診断がつく病気ではない
肺炎や急性膵炎や発作など、重症状態での血液検査の一環として甲状腺ホルモン(T4)が測定されており、軽度な低値で甲状腺機能低下症と診断され、主訴の病気の治療とともに甲状腺ホルモン剤が処方されている例を診ることが実際にあります。
甲状腺ホルモンは元気にする方向に働くホルモンで、その他の疾患の影響で下がることが分かっています。
理由は明確には解明されておりませんが、一説には体を安静にするためではないかと言われています。
甲状腺機能低下症ではないのに、その他の疾患の影響で甲状腺ホルモン値が下がることを、euthyroid sick syndromeと言います。日本語ではカタカナ読みでユウサイロイドシックとか、甲状腺機能正常症候群などと呼ばれます。
急性期にどうしても甲状腺ホルモン剤を使わないと救命率が下がるというケースはほとんどないのではないかと思います。粘液水腫性昏睡や、もしかしたら循環器への影響など、ごく限られた症例では急性期の仮診断・治療の必要があるかもしれませんが、私の考えとしては、肺炎や 膵炎、てんかん発作などの急性期にT4を測定する意義は低いと思っています。(測定しても良いと思いますが、それだけで診断するのは間違いだと思います。)
当院での診断
基本的に急性期に甲状腺ホルモン値の測定は行いません。
体調が安定していて、甲状腺機能低下症の疑いがある場合(健康診断を除く)にまず甲状腺ホルモンT4と甲状腺刺激ホルモンTSHを測定します。
この検査で、T4が測定限界未満かそれに近い値でTSHが高値であれば甲状腺機能低下症と診断します。
これらの検査で診断できない場合は、3-6ヶ月程度あけて再検査か、遊離型甲状腺ホルモンfT4を平衡透析法で測定します。遊離型甲状腺ホルモンは甲状腺機能低下症の診断に感度も特異度も高いと言われていますが、信頼性の高い結果を得るには平衡透析法での測定を依頼することが大切です。本稿執筆現在、IDEXXラボラトリーズ1社のみが商業ベースでの検査を行っており、米国に検体を輸送しての検査となるため結果が出るまで通常の検査よりも時間がかかります。
甲状腺機能低下症と診断したら生涯内服薬を続けることになりますので、診断には慎重を期しております。
投与開始後のモニタリングも重要
ほとんどのケースで何らかの症状があるはずですので、甲状腺ホルモン剤の投与で甲状腺機能低下症の症状が改善していくのか、また、血中甲状腺ホルモン濃度は適切なのか、というモニタリング検査は必須です。
どうしても診断的な検査結果が出ないけれども、甲状腺機能低下症の疑いが残るので試験的に治療したい、という場合には投与開始後の反応を診て治療的診断を行うこともあるかもしれません。(今のところ当院でそのような手順を取ったことはありません。)
その甲状腺ホルモン剤の内服は本当に必要ですか?
当院で甲状腺機能低下症と診断して治療している犬の飼い主様は、本稿を呼んでも何とも思わないと思います。当たり前ですよね。当院の診断手順なので。
当院の患者さまでなくても、適切な診断治療を受けているなら何とも思わないでしょう。
もし、本稿をご覧になって不安になる飼い主様がいらっしゃいましたら、はら動物病院までご来院ください。