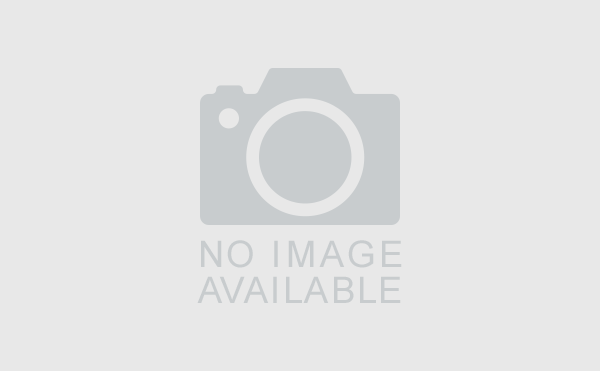はじめてのけいれん発作が高齢なら脳腫瘍や脳炎を疑う
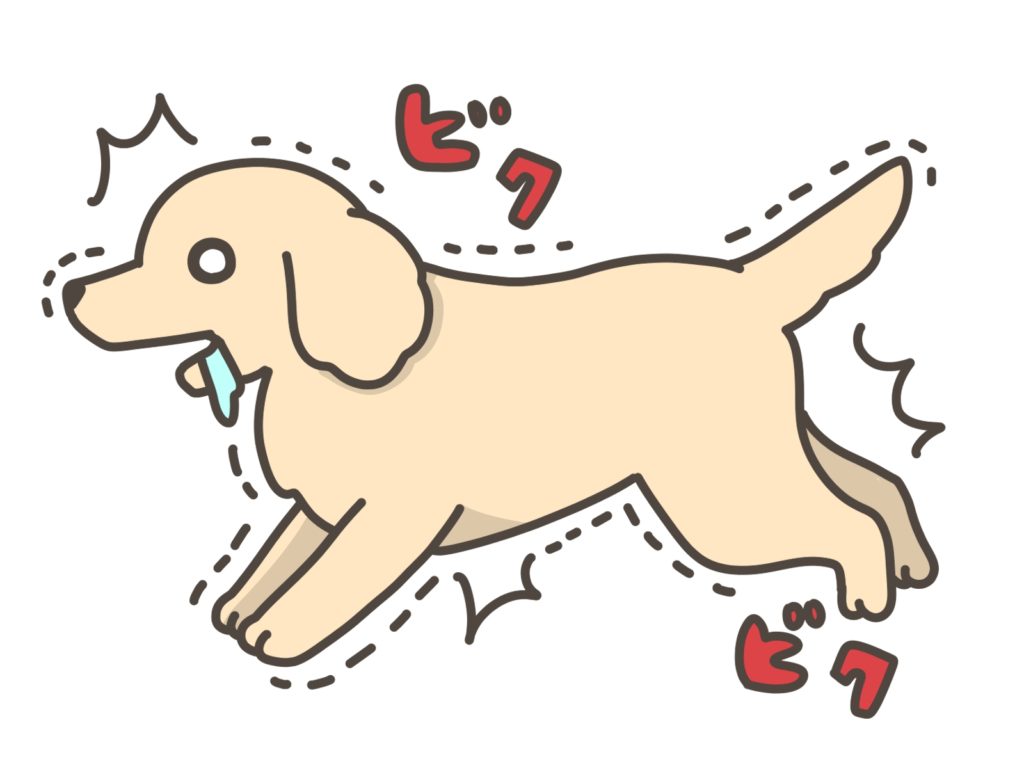
けいれん発作と言えばてんかんが有名ですね。犬にもてんかんがあります。
当院のような小規模の動物病院でも3頭以上の子達が特発性てんかんの継続治療中ですので、それほど珍しくはない病気です。
しかし、意識を失って硬直した後に痙攣する、強直間代性痙攣を引き起こす病気は特発性てんかんだけではありません。
情報の正確性を意識するとどうしても長くなってしまうので、最初に伝えたいことを書いておきます。
7歳以上ではじめて起きた発作は、脳腫瘍や脳炎の可能性が高いです。
言いたいことはこれだけです。
7歳以上ではじめて起きた発作なのに、脳腫瘍や脳炎の疑いに関して獣医師から言及がなかった場合、他の動物病院でセカンドオピニオンを受けることを検討しましょう。
てんかんとは?
意識を失うようなけいれん発作(強直間代性痙攣)が出たならてんかんでしょ。っていうのはその通りです。
ただ、てんかんといっても2種類あるのです。
現代の医学/獣医学では構造的異常が特定できない「特発性てんかん」と、脳腫瘍などの異常が特定できる「構造的てんかん」があります。
脳腫瘍も脳炎も血管異常も、脳が原因での発作は全部てんかんではありますが、特発性てんかんと構造的てんかんは治療方針や予後(生存期間)が大きく異なります。
特発性てんかん と 構造的てんかん
特発性てんかんは、原因は不明なので抗てんかん薬で対症療法を行うしかありません。
しかし、発作間欠期(発作が出ていない時)は無症状で、発作重積以外で生命に影響することはありません。発作のコントロールだけすれば良い病気です。
構造的てんかんは、発作重積が生命に関わることがあるのは特発性と同じですが、原因である腫瘍や脳炎の影響が生命維持を司る脳幹部まで達すればその影響で死亡することがあり得ます。
また、発作のコントロールという対症療法も必要ですが、原因である腫瘍や脳炎に対しての治療が必要であることは言うまでもありません。
脳以外が原因の発作=反応性発作
脳以外が原因の発作もあります。
子犬の低血糖や、門脈シャントや肝不全による高アンモニア血症など。
高脂血症による発作というのも、ケースレポート程度の報告はありますが極めて稀であり、総コレステロールもしくは中性脂肪値は少なくとも1000mg/dlを超えるような著しい高値でなければ起こりません。
IVETF 特発性てんかんの診断 Tier1
IVETF(国際獣医てんかん特別委員会)という団体が犬の特発性てんかんの診断基準を定めています。
Tier(信頼レベル)1~3までを定めておりますが、その中のTer1の基準を挙げます。
①24時間以上あけて2回以上の発作
②初めての発作が6ヶ月齢以上6歳以下
③発作間欠期の身体検査・神経学的検査・血液検査/尿検査に明らかな異常を認めない
細かい補足を除くと上記3点です。
初発の発作が6ヶ月齢未満だった場合には、低血糖や門脈シャント・その他の先天奇形などを第一に疑います。7歳以上が初発の発作であれば脳腫瘍などの構造的てんかんを第一に疑います。
まとめ
大事なことなので最後にもう一度書きますが、7歳以上で初発の発作は脳腫瘍や脳炎である可能性が高いです。
発作間欠期もいつもと違う様子があるなら、なおさら特発性てんかんの可能性は低いです。
脳腫瘍であっても腫瘍の種類や大きさによっては放射線治療で2年以上の長期の生存期間が期待できることがあります。しかし、同じ腫瘍でも大きくなってしまうと放射線治療の前に減容積目的の外科手術が必要になることがあります。そうすると、周術期に亡くなるリスクが生じますし、外科手術の分のコスト負担が必要になります。脳外科手術や放射線治療はそれぞれ100万円以上になると思われます。
飼い主様がご自身で愛犬/愛猫の病気や症状に関して調べたり、セカンドオピニオンを受けたりすることでより良い検査・治療を受けられることもあります。
自分のペットは自分で守るということを意識して、飼い主様が主体的に動くことが大切です。
脳神経発作に関してしっかり学びたい飼い主様は、一般向けにしてはかなり長いですが、IVETFメンバーでもある日本獣医生命科学大学教授の長谷川先生が「犬と猫のてんかん読本」を公開されていらっしゃいますので、以下のリンクからご覧ください。
https://nestle.jp/sites/g/files/yjnsyp131/files/brand/purina/csv/purpleday/dr.hasegawa.pdf