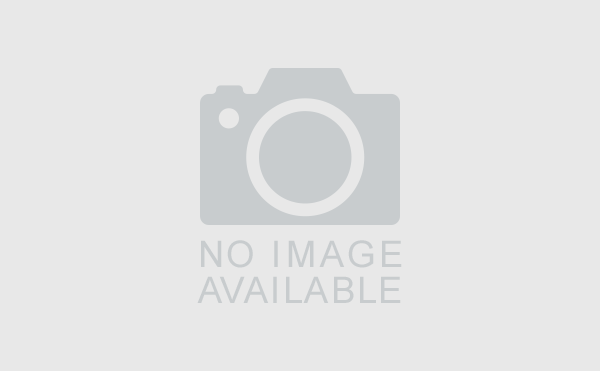小型犬の心臓病 僧帽弁閉鎖不全症の最新内科治療2025
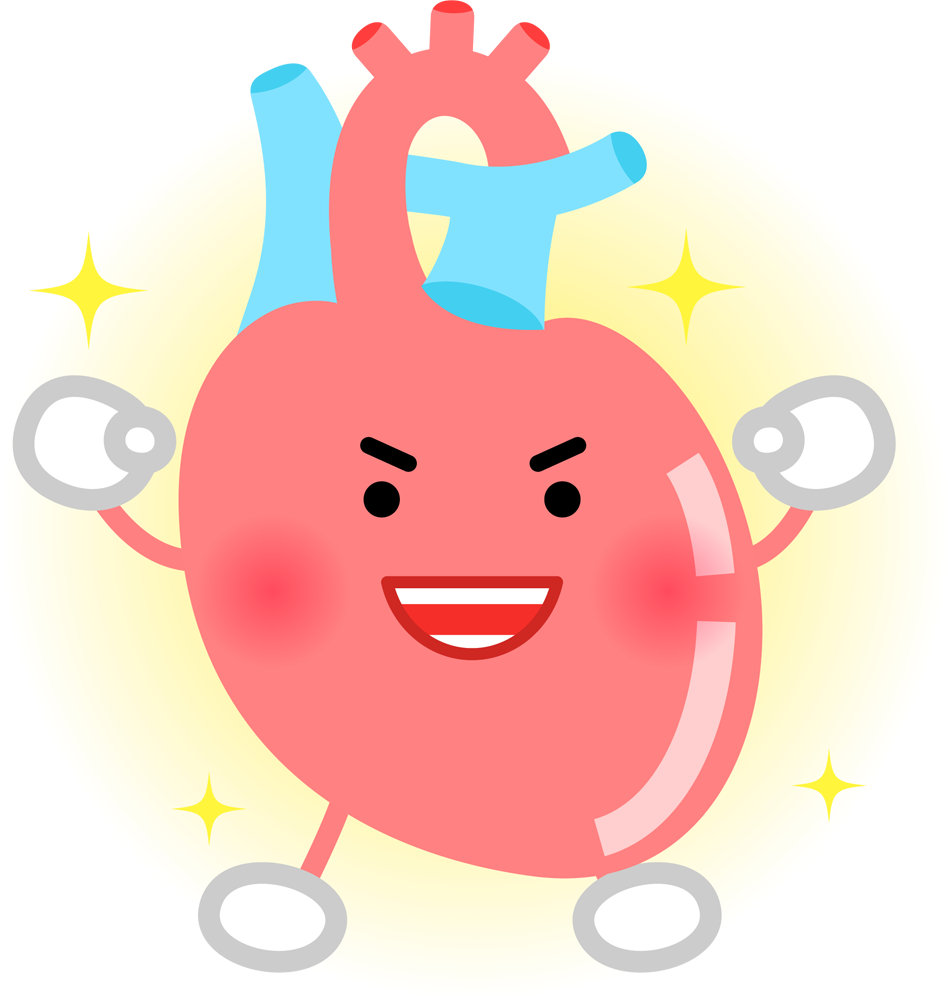
小型犬に非常に多い心臓病である僧帽弁閉鎖不全症という病気があります。
いわゆる心臓弁膜症ですね。
左心房と左心室を隔てる僧帽弁という弁がしっかり閉まらなくなる病気です。完全に閉じない隙間から血液が逆流する影響で徐々に心不全に進行します。
これを治すには、弁が閉じるようにすればいいわけです。基本的には外科疾患なのです。弁の閉鎖不全が原因なのですから手術で弁が閉まるようにするというのが最も適切な治療です。
小型犬での僧帽弁閉鎖不全症は手術例も増えてきており、成功率も90%を超える施設が多いようですので、手術が可能であればそれが一番良いと思います。
ただ、動物医療に公的保険はありません。任意保険に入っていたとしても限度額制限がありますので、保険で賄える割合はそれほど大きくないと思われます。おそらく200万円前後程度はかかるようですので、なかなか誰しもが手術の選択を取ることができる状態にはありません。
小型犬は心臓が小さく手術が難しいので、カテーテルで人口弁を入れるという選択肢も出てきているようです。しかし、日本人は手先が器用な人が多いのか心臓外科手術ができる施設が増えており、カテーテル治療はあまり普及が進んでいないように思います。カテーテル治療では逆流を完全に制御することはできないようです。
外科手術やカテーテル治療は大学病院等の専門施設でないとできないので、当院のような街の一般的な動物病院では内科治療を行っています。
一般的な内科治療のおさらい
ACVIM(米国獣医内科学会)のコンセンサスステートメントに基づく治療が標準的です。
心雑音の大きさ、レントゲンでの心臓の大きさ(椎体心臓サイズ)、エコーでの左心房・左心室の大きさの全てが一定基準以上であれば、無症状でも治療を開始しましょう、というのが現在の標準治療です。
この状態をstage B2といいます。
一度でも肺水腫(心不全症状)を起こすとstage C、標準治療でコントロールが困難な状況がstage Dです。
stage B2の治療
強心+血管拡張薬であるピモベンダンを内服します。
stage B2では、飼い主さんが気づかない程度の軽度な活動性低下が出ていることも多く、内服を開始すると「元気になった」と喜んでいただくことが多いです。
stage Cの治療
ピモベンダンに加えて、利尿剤を投与します。当院では基本的にトラセミドを使用しています。
また、血管拡張薬のACE阻害剤も使用が推奨されます。
内服薬の数が増えても飲めるのであれば、アルドステロン拮抗薬のスピロノラクトンも推奨されます。
ガイドライン入りが期待される新たな治療薬 ARNI
心臓に負荷がかかると分泌されるANPやBNPなどのナトリウム利尿ペプチドというホルモンがあります。
利尿作用や血管拡張作用、心筋保護作用などの効果を持ちます。
しかし、このホルモンはネプリライシンという酵素により分解されてしまいます。
ネプリライシンを阻害することでナトリウム利尿ペプチドを高濃度に保つための薬がサクビトリルです。
しかし、ネプリライシンはナトリウム利尿ペプチドだけでなく、アンギオテンシンⅡという血圧を上昇させるホルモンも分解しているので、サクビトリルの単独投与はアンギオテンシンⅡを増やして血圧上昇の悪影響が出てしまう可能性があります。
この副作用はアンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)で防止できます。そこで、サクビトリルにARBであるバルサルタンを配合したのがARNI 商品名エンレストです。
stage Cの僧帽弁閉鎖不全症犬に対する短期投与試験では、心臓の大きさが有意に縮小(改善)しています。
https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2021.700230/full
もっと最先端 SGLT2阻害薬
尿中への糖排泄を促進するSGLT2阻害薬は、人では糖尿病以外にも心腎保護効果が期待できることがわかっており、既に臨床応用されています。
動物では、おそらく現在臨床研究が進行中という段階で、現時点(2025年7月)で発表されている臨床研究報告は私の知る限りはありません。
近位尿細管でのナトリウム再吸収抑制によるループ利尿薬の反応性改善と、糖による浸透圧利尿効果のダブルの効き目が期待できるため、どうしても困ったら使ってみる価値はあるかもしれませんが、まだ臨床研究報告も出ていないような薬なので基本的にはまだ街の動物病院で使うような薬ではないと考えた方が良いでしょう。
まとめ
エンレストは臨床試験での用量も公開されておりますので、使用しやすい段階になってきていると思います。
stage Cでは拡大した心臓が小さく戻ってくれる効果が確認されているので、既存の治療では良好な生活の質が保てない場合には試してみる価値があると思います。ただ、2025年現在の標準治療ではないことには注意が必要です。
SGLT2阻害薬も使用の候補にはなりますが、臨床研究発表はまだない薬です。その他全ての治療を試したけれどもうまくいかない場合に限り、実験的な使用となることを飼い主様が理解して受け入れるのであれば使うことがあるかもしれない、くらいの位置づけです。
当院では、病気と戦う武器として、ガイドラインの一歩先の知識も仕入れるように努力しております。
愛犬が心臓病で治療しているけれども発咳が改善しない、肺水腫での入院を繰り返している、などでお困りでしたら、はら動物病院の受診をご検討ください。